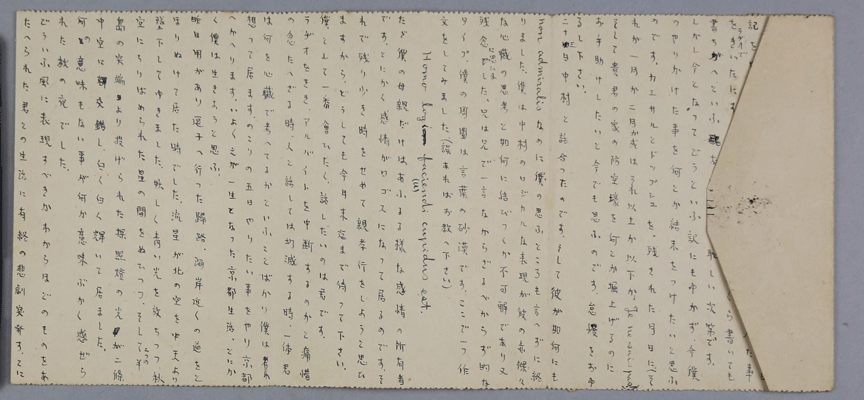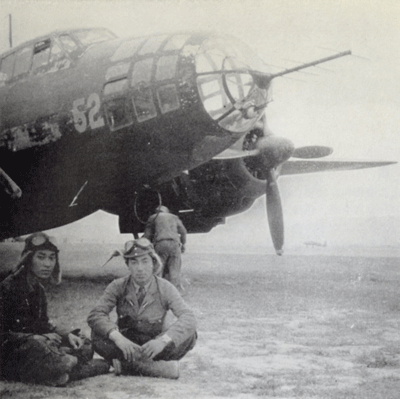第1章 林尹夫
1922(大正11)年、神奈川県の旧家の次男として誕生した尹夫は、13歳の時に父を亡し、家計を支えた兄のもと、横須賀第二中学校から京都第三高等学校(三高)、京都帝国大学(京大)へと進学します。
日本が満州事変、日中戦争へと突き進む中、三高時代には、恩師深瀬基寛や、親友の中村金夫らと出会い多感な青年時代を過ごしました。1年間休学して語学を学び直し、フランス語、ドイツ語を原書で読みこなす才能は、友人たちの誰もが認めるところとなりました。京大史学科西洋史学専攻に進学後は、やはり親友の大地原豊らとともに、若者らしい悩みを抱えながら学業に励む学生生活を送っていました。
尹夫の人生が一変したのは、1943年10月、在学徴集延期臨時特例が出された時からです。それまで軍隊への徴兵が猶予されていた大学生、生徒も将兵として戦地へ駆りだされることになったのです。同年12月、中村や大地原、そのほか多くの同級生らとともに尹夫は軍隊へと入隊します。
海軍飛行科予備学生第14期生として、横須賀第二(武山)海兵団、土浦航空隊、大井航空隊での訓練を経て、海軍少尉となり海軍航空隊偵察要員として1944年5月ごろ美保航空基地へ配属されます。
偵察飛行のため大和基地を飛び立ち四国沖で消息を絶ったのは、1945年7月28日未明のことでした。
「遺稿ノート」 四冊
B4判横罫ノートの表紙に、のちに他者が書き加えたとみられる「遺稿Ⅰ」「遺稿Ⅱ」「遺稿Ⅲ」「遺稿Ⅳ」の文字がある林尹夫の日記。1940年4月6日から1945年7月ごろまでの記録である。「遺稿ノートⅠ、Ⅱ」では在学中の読書歴をふくめた勉学に関すること、友人との関係など青年らしく自分と社会との在り様、性、将来についての悩みを率直な文体でつづっている。
「遺稿ノートⅢ」は、軍隊での訓練中の記録であり、軍隊生活の非合理性、理不尽さに肉体的にも精神的にも挫けそうな中でも、外国語を学び続けた様子がわかる。
「遺稿ノートⅣ」では、生と死の極限にある状況下で親密さをます友への情に倒錯していく気持ちを、断片的に、時に激情にかられた筆致で書き記しながら、友人、恩師への思い出と別れの言葉が繰り返される。
ー1945年7月15日で親しい人とおわかれのようだ、今年の夏を生きて迎えることができないーという記述もあり、具体的かつ確実に死を予感してたようである。また、同時期に学徒出陣したものたちが多く配属された沖縄への特攻作戦の前線基地の一つ、鹿屋航空基地を訪れたときには、爆撃され閑散とした格納庫に日本の敗戦と自らのたどる道を目の当たりにした絶望を伝えている。
陶酔とも諦念ともとれるそのさまを、克也は「正常な狂気」に至ったと表現した。
美保での夜、二人して夜見ヶ浜の砂浜で過した。彼はわたしに三つの事を託した。
第一は、これ以上、この戦争で青年を殺すような行動は断じて阻止するようにしてくれ。そのために「俺たちは死ぬことを甘受するんだ」と言った。
第二は、日本が占領されたあと、日本の再建のために、「なによりも青年のことを最大限に考えてくれないか」と言った。
第三は私たち個人のことだった。
わたしは彼と多く語り合ったなかで、「絶対に死なないようにしろ。生きるのだ」しかし彼は「もう、手遅れなんだ」と呟やくように答えた。
林克也
「愛と苔の下で」『潮 昭和四十一年八月号』(潮出版社 1966年)
「葉書(大地原豊宛て)」
1943(昭和18)年9月25日
ラジオで在学徴集延期の停止が放送されたときショックをうけたと、心境を語っている。
―どういう風に表現すべきかわからに(ママ)ほどのものをあたへられた君との生活に 有終の悲劇突発す、とにかくvivre,vivre(生きる)と思ふのみです。―
この時以降、陸軍に入隊した大地原豊、同じく海軍の兵科に入隊した中村金夫らとは、訓練時代を通じてお互いにはがきのやりとりをしながら、励ましあった。恩師、深瀬基寛ともまた、書物を読んだ感想、学問についてなど便りを交わした。
十一月二十九日、私の最後の夜を林君は私の家で送ってくれた。それは私が時代に対し—皮膚的には町内会・隣組に対して—ただ一つしたかった反抗に、加担してくれるためだったか。三十日午前三時、二人はそっと起きて、だれにも万歳をいわれることなく、眠っている京の街を北から南に駅まで歩き抜けた、途中から加わってくれた中村君(やはり海軍)と三人で。着いた駅頭はすでに学徒兵を送る旗幟でうずまり、私どもは早々に別れたと記憶する。運動部時代のバッグ一つもってフォームに向う私を、「ハイキングに行くみたいね」と笑ったのが、林君から聞く永久に最後の肉声となった。
大地原豊
「若き二人のフィロローゲンよ」『わがいのち月明に燃ゆ』(林尹夫 筑摩書房 1967年)
翌二十七日は私の誕生日であったが、急にその夜、林の機が南方海面を哨戒することになった。私たちは昼間、付近を散歩しながら、明日はこの池で釣をしよう、と目当てをつけたり、誕生祝いは一日延期しようと約束した。
(中略) 時間が来て搭乗員の乗るトラックが来た。何もしてやれない私は、林を呼びとめて、アメを一つ口中に放り込んだ。林はトラックの上で手を挙げた。夕やみの中で笑っているように見えた。
佐竹一郎
「回想の林尹夫少尉」 『展望』5 筑摩書房 1967年